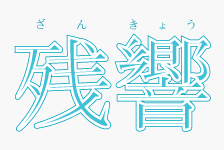5.リビングの海
クラムチャウダーのブランチを楽しんだ勉と日咲子は、昼過ぎに家を出て件の雑貨店に向かった。
勉の予想通り、雑貨店は大いに日咲子のお気に召したようだ。店の作りを可愛いと褒め、品揃えが素敵だ、と褒める。
フォトフレームのコーナーから始まって、文具も、小物も、アクセサリーも、日咲子はじっくり堪能した。中でも一番長く足を止めたのは、アロマキャンドルの棚だった。
やわらかなパステルカラーに彩られた、手のひら大のキャンドル達を見た日咲子は、ほうっとため息をつき、中のひとつをそっと手に乗せた。他の客がその棚にやって来なければ、いつまでもいそうな雰囲気だった。
店内をぐるりと一周して、最後に日咲子はもう一度アロマキャンドルの棚に戻ってきた。
「……勉君、今日は見るだけのつもりだったんだけど、買ってもいいかなあ」
あまりに申し訳なさそうに言うので、勉はついふきだしてしまった。
「大丈夫。これひとつ買うくらいは問題ないよ」
「うん、そうだよね、やっぱりひとつだよね」
「……何個買うつもりだったんだ」
それには答えず、日咲子はうーんと悩み始めた。どうも気になる香りが何種類かあるらしい。くんくんとキャンドルを香りながら、これも素敵、あれもいい香りと呟いている。
そうやって十分ほどたっただろうか、日咲子の手には二つのキャンドルが残った。
ひとつはフレッシュな桃の香りのキャンドルで、もうひとつは南国の海を思わせる爽やかな香りのキャンドルだった。
二つを手にしたまま、日咲子はまだうーんと唸っている。どうにも選びきれないらしい。
「桃の香りもいいけど、それだとなんだかお腹が減りそうな気がする」
勉の冷静な意見に、思い当たるフシがあるのか、日咲子はこくこくと頷いた。そっと桃のキャンドルを棚にもどす。
相原家には南国の海を思わせるアイランドというアロマキャンドルがやって来ることになった。
家に帰ると、日咲子はさっそくアイランドをリビングに置いた。爽やかな香りがほのかに漂う。明日の朝にはきっとリビング中に広がっていることだろう。
「楽しみだね」
「うん、でも今日は早く寝なよ」
勉は食後の雑務を引き受け、日咲子を早々にベッドへと追いやった。果たしてそれは正解だった。早起きして料理を作り、久々に遠出をした日咲子は、翌朝熱を出してダウンしてしまったのだ。
「……三十七度四分」
体温計の数字を読み取り、勉は苦笑した。
「やっぱり出かけたのがまずかったかな。ごめんな、日咲子」
「そんなことないよ。これくらいの熱だったら、今日一日ゆっくりしてたら治るから。身体はちょっと辛いけど、心は元気」
「俺、洗濯と掃除してくる。薬は飲んだ? よし、じゃあそのまま寝てろ」
「勉君、ありがとう。ごめんね」
手早く家事をかたづけた勉は、リビングのカウチにクッションとタオルケットを運び、たっぷりのアイスティを用意した。親戚のおじさんから中元でもらったフルーツゼリーもガラスの器にもりつける。アイスティとゼリーをサイドテーブルに置くと、押さえ目のボリュームでCDをかけた。女性シンガーの静かな歌声が響く。
用意をすっかり整えて、勉は日咲子を迎えに行った。
「日咲子、せっかくだから今日はすごく贅沢にゆっくりしよう」
きょとんとする日咲子をベッドから抱き上げて、リビングのカウチへ連れて行く。
日咲子をクッションにうずめるように寝かせると、勉も隣に身体を投げ出した。
「どう? ベッドにいるよりいいだろ」
「……素敵。勉君、どんどんわたしに感化されちゃうね」
「日咲子ももう少し俺に感化されて、賢くなったらいいのにな」
「賢いもん。わたし、ちゃんと賢いもん」
ふくれる日咲子に、勉はアイスティを差し出した。とたんに機嫌を直してグラスを受け取った日咲子は、そうだ、と呟いた。
「ねえ、勉君。電気をつけて、カーテンを閉じてよ。あ、窓は少しだけ開けてね」
意図が読めないまま、勉は日咲子の言葉に従う。
「ほら、海みたい」
リビングのカーテンは深いブルーで、微かに入り込む風がそれを揺らすと、確かに海を思わせなくもなかった。
「歌声が波音で、海辺のリゾートの香りがするよ」
日咲子はCDとアロマキャンドルの力を借りて、リビングにくっきりと海を作りだす。
「本家には適わないな」
勉はまいった、と言ってカウチに戻った。
「さっきの言葉は取り消すよ。日咲子は賢い。日々を楽しく過ごす天才だ」
「うん。わたし、楽しい事見つけるの得意だよ。人を笑顔にさせたり、元気付けたりするものって、すごく近くに沢山あるの。でも、気づかないで素通りする人も多い。わたし、その人達の分も拾い上げて、元気をもらうの」
熱を帯びた日咲子の手が伸びてきて、ぎゅっと勉の手を握り締めた。
「勉君が一緒にいてくれると、それがとても上手にできるんだよ。勉君、ずっと一緒にいようね。二人で沢山、笑顔の元を見つけよう」
「うん」
勉は、日咲子の手をタオルケットの中に戻すと、頷いた。二人を静かに、リビングの海が包み込んでいった。