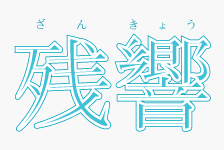1.アネモネ
エンジン音を軽快に響かせながら通り過ぎる車のヘッドライトが、勉の陰を長く引き伸ばして連れ去った。
吹きつけられるほこりっぽい風から顔を背けたとたん、疲れた表情の男と視線がぶつかり、ぎょっとして足を止める。
「……なんだ」
勉が苦笑を浮かべると、その男も同じ苦笑を唇に刻んだ。なんのことはない。男は、遅い夏の夕日に照らし出された硝子に映る、勉自身だったのだ。
額にふつりとにじむ汗までが落日色に染められて、随分と暑苦しい。クールビズが提唱されてはいたが、今日は顧客の事務所へ出向いていたため、スーツ姿だ。
ふう、とため息をひとつついて、几帳面にしめたままだったネクタイをゆるめる。本当は乱れた髪も直したいところだが、鏡代わりの硝子は可愛らしい雑貨店のショーウィンドウだったので、これ以上姿を映し続けるのは気が引けたのだ。センス良くディスプレイされたアクセサリーや小物類が、濃灰のスーツと調和を奏でることはないだろう。
まるで勉を追い払うかのように、小さなピアスがチカリと光った。しかし、その輝きよりも鮮やかな色彩が勉の目を奪う。セールの札のついたカゴにもられた、色とりどりの端切れの山――。
「なにやってんだ、相原!」
ついて来る様子のない勉に気づいたのか、先を歩いていた同行の営業が振り向いて叫んだ。
「岡野、今日はもう直帰だよな?」
端切れに視線を固定させたまま勉は問うた。岡野はチラリと腕時計を確認して、もう一度叫ぶ。
「定時は過ぎてるし、帰ってからの打ち合わせもないし、連絡も入れてあるんだから直帰で問題ないだろ。たまにはこういう日もないとなあ」
「よし、じゃあ、お疲れ様」
「なんだよ、お前も駅まで行くんだろうが」
「俺、寄り道するから」
岡野にひらひらと手をふると、勉は雑貨店の扉をくぐった。先ほど目をひいた端切れの山から、しばらく迷った末、一枚を選び取り購入する。
小さな包みを手にして店を出ると、岡野は缶コーヒーを飲みながら、ご丁寧に勉を待っていた。
「暑いだろ、先行っててよかったのに」
「喉渇いてたからな。飲みきっても出てこなかったら行ってたよ」
岡野は軽やかな手つきで、飲み終わった缶コーヒーを専用のクズカゴに捨てた。ガランという音を背に、どちらからともなく並んで歩きながら、駅へと向かう。
「えらく熱心に見てたけど、何買ったんだ?」
「ああ、これ?」
勉が包みを持ち上げると、その可愛らしいパッケージを見て、岡野はうへえと笑った。
「奥さんへのお土産か? そういや、OLの皆様方が相原サンは愛妻家って噂してたっけ。お前、そういう店に詳しいんだってなあ」
「噂になるほど、特別愛妻家ってわけでも、こういう店に詳しいわけでもないよ」
勉の淡白な答えが気に入らなかったのか、岡野はフーンと唇をゆがめて頷いた。ふ、と笑って勉は続ける。
「世界ってさ、実は広くて狭いよな」
「なんじゃそりゃ。昔からそんなことは言われまくってるだろ。なんだよ、あの店に転校していった元同級生がいて奇跡の再会でもはたしたか」
「そういうんじゃないよ。例えばさ、さっきの店でもさ。普通男は視界に入っても頭には留まらないだろ? ただの景色の一部。つまりそこに存在してても、ないのと同じで、多くの男の世界には関わりないものってわけだ」
「まあなあ。そういう所で働いてるか、そういうのがすごく趣味ってヤツ以外はまあそうだろうな」
岡野自身がそうだった。勉が言った通り、先ほどの雑貨店など、辺りの公園や電柱と同じ風景の一部でしかなかった。
「すごく沢山の物が世の中には”ある”のに、無意識の内に切り離して”ない”事にして生きている」
「そういう事を教えてくれたのが、奥さんか」
からかいを含んだ岡野の声に、勉は首を振った。
「違うよ、あいつはそんな事を言葉に出来るほど頭がよくない」
お前それ酷い、という岡野の言葉を、勉は涼しい顔で受け流した。
「自然とさ。一緒に暮らして、一緒に行動する内に当然あいつの興味があるものに関わるだろ? いつからか、それが俺の世界を広げてくれていたんだ」
広げた、ではなく、広げてくれていたという言い回しに、勉の思いが滲んでいるようだった。
「これ、何柄だと思う?」
唐突に勉は手にしていた包みを岡野に見せる。透明なパッケージは中身が良く見えた。丁寧に折りたたまれたベージュ色の布が入っている。ランダムに散った模様をチラリと見て、岡野はあっさり答えた。
「何柄って、花柄だろ」
「五十点」
「ああん?」
首を振る勉に、岡野は眉をひそめる。
「花だろ、花。どこからどうみたって、花じゃねーか。いくら俺が朴念仁だからって花を別の何かと見間違えるほど鈍くはねえぞ」
確かに、布にプリントされているのは岡野の言うとおり美しい花模様だった。
「花にもいろいろあるじゃないか」
ゲッと岡野は目を見開く。
「待ってくれ、自慢じゃないが花になんか詳しくねえぞ。チューリップとひまわりくらいなら判別がつく!」
「俺も昔はそうだった。まあ、俺の場合はそこに薔薇もプラスだったけど」
つまり描かれている花は今話題に上った三種類以外ということらしい。
チューリップでも、ひまわりでも、薔薇でもないその花は、ぷっくりと丸い暗紫色の花芯の周りを、緋や藍といった鮮やかな色の花弁に縁取られ、見えない風にそよいでいた。
「アネモネだよ」
それが、どことなく少女の纏うドレスを思わせる美しい花の名前だった。
「不思議だろ。名前を知ったらどことなく違って見えないか?」
「ただの花じゃなくて、アネモネかぁ」
くくっと岡野は苦笑する。岡野からすればやはり勉の話は多分に女性的過ぎた。しかし、確かにもう、ただの花柄とは思えないのも事実だった。名前を得たアネモネは、確固たる存在を岡野に主張してくる。つまりこれが、勉の言う世界が広がるということなのだろう。
「お前、もてるんだろうな」
しみじみ呟く岡野に、勉はうそぶいた。
「今更もてる必要性は感じない」
はっきりしたその答えに、とうとう岡野もあてられきって、参ったと手を上げた。
二人は顔を見合わせて笑うと、また週明けに、と駅の改札で別れた。