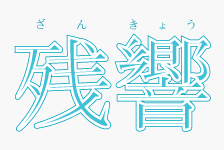2.一番大切な
岡野と別れた後、JRとバスを使い勉は自宅マンションへと帰ってきた。その間、何度か帰宅の電話を妻に入れたが、つながらない。自宅の電話も携帯も留守番電話に切り替わるだけだ。時刻は十九時半で、常ならばとっくに妻は自宅にいる時間だった。
やっと夜の気配が漂い出した空を背に、勉は丁度やってきたエレベーターに乗りこんだ。自宅のある八階へ向かう。
扉を開けると玄関に、妻お気に入りのパンプスが転がっていた。
いったいどうやって脱げばこうなるのか想像しにくいが、右は完全に裏返って靴底が見えていたし、左はいっそ拍手をしたくなるようなバランスで側面を下にして美しく立っていた。二つ並べばまるでカタカナのソのようだ。
玄関では履物をそろえるように、というルールを声高に振りかざすのは妻の方なのだが、しばしばこのルールは妻に適用されなくなる。
ただいま、と言ってはみたが、応えはなかった。代わりに、こうこうとついた廊下の電気と、開け放たれたままの洋室のドアが勉を出迎えてくれる。
勉は自身が脱いだ革靴と、散らばったパンプスを共にきちんと並べると、ゆるめていたネクタイを外しながら廊下を歩いた。
そっと洋室をのぞくと、ドアの前にこれまた妻の気に入りの白のバッグが放り出されている。横転したバッグは、遠慮なく財布や携帯を吐き出していた。携帯はチカチカと点滅して不在着信があった事を知らせているが、主の興味を引くことはできなかったようだ。
当然のように着替えもすませていない妻は、一心不乱といった様子でデスクトップパソコンに向かっていた。細い指が踊るようにキーボードとマウスの間を動き回っている。
勉はかすかな苦笑をひとつ浮かべると、静かに洋室から離れた。着替を済ませ、夕食の準備にとりかかる。昨日買い物に行ったばかりらしく、冷蔵庫の中の食材は豊富だった。
「さて、どうしようか」
思案するような言葉を口にしながらも、勉は手早く食材を取り揃えていった。
玉ねぎをざくざく刻み、ムキエビと缶詰のとうもろこしを加えて、一口サイズのかきあげを作る。みょうがやネギといった薬味をそろえ、たっぷりのカツオで出汁をとる。
ぷん、と日本らしい良い香りがキッチンに広がった。
「あれ、美味しそうな香りが……」
鼻をくんくんいわせながら、妻が洋室からさまよい出てきた。
「ただいま、日咲子。もうすぐ出来るよ、ひやあつうどん。かきあげつき」
あつあつのつゆに、冷たく冷やしたうどんを合わせたひやあつうどんは、相原家の夏によく登場するメニューで、二人とも大好物だった。
歓声を上げかけて、日咲子は我に返る。
「つ、勉君、いつ帰ったの?」
「見たらわかるでしょ、そこそこ前だよ。電話もしたけど、気づかなかったみたいだね」
日咲子は、もじもじと祈るように手を組みながら小さな声で言った。
「ごめん、すぐ手伝うね」
「いいよ。もうほとんど終わりだから着替えておいで」
無言で着たままのワンピースを視線を落とした日咲子は、こっくりと頷くと洋室へ駆け込んでいった。
勉は笑って料理のしあげにかかる。
かきあげをもりつける間に、ルームウェアに着替えた日咲子が戻ってきた。いそいそとグラスや箸を食卓に並べているのは、きっと罪滅ぼしのつもりなのだろう。
かきあげに、うどんに、ビールに麦茶、最後に茹でて冷やしてあった枝豆を出して夕食の準備は完了だ。
相原家ではテレビを見ながら夕食をとるのが習慣で、ニュースやバラエティを見ながら二人で笑ったり、今日あった事を話したりする。
「勉君、今日は早かったんだね。わたしびっくりしちゃったよ」
飲酒運転の交通事故のニュースが終わったところで日咲子が言った。
「うん、お客の所に行ってたんだけど、会社に戻ってからの仕事がなかったから。やっぱりこの時間に帰ってこられると楽でいいや」
「――勉君が早く帰ってくるとわたしも嬉しいな」
「美味しいものにありつけるし?」
「そう、美味しいものに……、勉君」
うっかり頷いてから、日咲子はうらめしそうに勉をにらんだ。唇をつきだしたその表情はまるきり拗ねた子供で、大人っぽい日咲子の顔立ちに、似合わないことおびただしい。
日咲子はすっきりとした目元が涼しげな美人だった。外では無口になる事もあって、出来る女に見られる事が多いのだが、その実中身は非常に能天気で幼く、不器用だ。電卓を三回叩いて三回とも違う計算結果になるという素晴らしい特技をもっている。
知り合った当時、日咲子のあまりに外見とは異なる中身に勉はおののいたものだ。
もっと落ち着いた人かと思った、と言った勉に、日咲子は今とまったく同じ顔でぶんむくれたのだった。
「オットの帰りを喜ぶツマのいじらしい心をもてあそんだ!」
すっかり機嫌を損ねた日咲子は、泣きまねまで始める。またその泣きまねが小学生レベルで、えーんとわめきながらチラチラ様子を伺うのがなんともわざとらしい。きっと、外での”出来る”日咲子しか知らない人が見たら、かつての勉と同じく驚愕の極みを味わうことになるだろう。
食事を終えた勉はさっさと食卓をかたづける。日咲子はなんと、泣きまねをしながら空になった食器を差し出してきた。
たまらなくなって勉は笑い転げる。
「傷ついた妻を演じるなら、そこは食器出しちゃダメだと思うんだ」
「うん、わたしもそう思った」
日咲子も笑って、結局二人は仲良く後片付けをする。器用な勉が食洗機に食器を並べ、その間に日咲子が食卓を熱い布巾で拭く。
食洗機に入らない大きな鍋は、勉が手早く洗って流しの下の開きにしまった。
片づけが終わると、日咲子がぺこりと勉に頭を下げる。ショートカットの黒髪がさらさら揺れた。
「勉君、一週間お疲れ様でした」
「日咲子もお疲れ」
「うん。――勉君、ごめんね」
このごめんね、は帰ってきたことに気づかなかったごめんね、ではないだろう。
「気にしなくていいって言ってるだろ」
「うん、そうだけど。やっぱり気になっちゃうんだよ。前はさ、もっと忙しくて勉君大変そうだったけど、いきいきしてたから」
前、というのは勉が今の会社に勤める以前の事だ。専門学校を卒業した勉は、デザイン事務所に就職し、コンピューターグラフィックスを主とした仕事をしていたのだ。
CMやテレビに使われるグラフィックや、アーティストのプロモーションビデオ等も手がけていた。すさまじく忙しかったが、やりがいのある充実した日々だった。
未練がないと言えば嘘になる。やりたくてやっていた仕事だ。就職活動だって大変だった。
「わたしのせいだもん。ごめんね、勉君」
勉がデザイン事務所を辞めることになった原因は確かに日咲子だ。
日咲子は生まれつき虚弱な体質で、人より体力がない。普段はいたって元気そうなのに、すぐに熱を出したり、倒れたりする。昔は、三日間続けて学校に来られることを奇跡と言って喜んでいた。
そんな日咲子だったから、就職して働く事はとても大変だったようだ。ようだ、というのは勉がそれに気づかなかったからである。
結婚前は家族の手厚いフォローがあってなんとか勤め上げていた日咲子だったが、勉と結婚し、家事と仕事の両方が肩に乗ったとたんうまくいかなくなった。
勉は、日咲子の身体の事を、わかっているつもりでわかっていなかったのだ。自分の仕事の忙しさにかまけ、日咲子を省みることをしなかった。
気づいた時には、日咲子がパンクしていた。
散らかった家、休みがちゆえに肩身の狭い職場、なかなか理解されない体調の事……、ストレスを溜め込み、体力を使い果たした日咲子は、大きな帯状疱疹を作って倒れた。
入院とまではいかなかったが、一週間近くの安静が必要になった。
丁度大きな仕事を任されていた勉は、日咲子の実家に頼んで日咲子を預かってもらった。
やっと仕事を終えて日咲子を迎えに行った時、勉は日咲子と、日咲子の家族を交えこれからの事を話し合った。
日咲子は、家族の手助けなしには普通の生活が送れない。そして、結婚した今それをしなければならないのは勉だ。ただ働いて月給を家に入れ、日咲子と笑ったり、喋ったりしているだけではいけないのだ。
デザイン事務所に勤めていたら、残業や土日出勤は当たり前で、日咲子の事を気遣う余裕がない。
離婚の話も出たが、即座にそれは嫌だと思った。
勉は、悩んだ結果自分の夢を捨てた。日咲子は泣いてダメだと言ったが、聞き入れなかった。
「あの時言った言葉に嘘はない。今も思いは変わらないよ。俺は日咲子と暮らしていくことが一番大切なんだ。あの時気づけてよかったよ」
勉の言葉に、日咲子はうつむいてもう一度ごめんね、と言った。
「会社辞めたのは、俺だけじゃないでしょ。日咲子だって仕事好きだったのにさ」
「わたしは、しょうがないよ。いくら好きでも、続けられない」
「本当は家でゆっくりさせといてあげたいんだけど。ごめんな、稼ぎ悪くってさ」
「そんなことないよ! 勉君はがんばってるよ! それに、週に四日のパートくらい、わたしでも出来るよ!」
「じゃあさ、せっかくの週末の夜をごめんねって言い合って過ごすのやめない?」
ほんとだね、と言って日咲子はやっと笑った。その笑顔を見て、ああ、と勉は思う。
この笑顔こそが、自分の新しい、一番大切な夢なのだと。