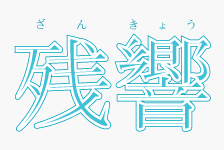4.あさりとミルク
携帯のアラームで勉は目を覚ました。時刻は午前十時。休日の朝はたっぷり睡眠をとるのが相原家の決まりである。
雑貨店に出かけるのは昼からの予定なので、時間の余裕は充分だ。
「日咲子、時間だよ。起きな」
自身もまだ半分寝ながら、隣の日咲子を起こす。
「日咲子?」
しかし、返事はない。
どちらかと言えば、朝は日咲子の方が強くて一度のアラームで完全に目覚め、即座に活動のスイッチが入るタイプである。しかしそれは、仕事がある日に限ってのことだ。休みの日は体力回復をかねてたっぷりと朝寝を楽しむので、勉より早く起きたためしがない。なのにその日咲子がいないのだ。
「……雨か?」
酷い事を言いながら、勉は目をこすりベッドから降りた。寝室のカーテンを開けると、今日も気持ちよく晴れている。
寝室を出ると、ダイニングからさっと日咲子が顔を出した。
「勉君、おはよう。ブランチ出来てるよ。食べよう、食べよう」
勉は日咲子にせかされて、顔を洗って歯を磨いた。さすがにすっきりして、ダイニングに向かうと、日咲子が得意げな笑みを浮かべて勉を見つめる。
食卓にはなかなか豪華なブランチの用意が整っていた。
「日咲子、これ、時間かかっただろう」
「まあね。でもほら、昨日は夕飯作ってもらったし、御土産買ってきてもらったし、御礼なのです」
御礼の言葉通り、並んだ料理は勉の好物ばかりだった。
厚切りのトーストは半分にカットされ、ハチミツバターが添えてある。トマトとレタスと小エビのサラダに、つやつやしたグレープフルーツ。水滴の浮いたグラスにたっぷり注がれたアイスティ。
中でも勉が一番喜んだのは、大きなスープカップからほこほこと湯気を吐き出す、クラムチャウダーだった。野菜と殻付きのあさりを、ミルクとコンソメで煮込んだスープで、仕上げにパルメザンチーズがふりかけてあるのが日咲子流だ。
勉と日咲子は行儀良く手を合わせていただきますをすると、それぞれ料理に手を伸ばした。
勉が木の匙でクラムチャウダーをくるりとかき混ぜると、ミルクと海の香りが混然となってふわりとカップから立ち上る。
溶け出した野菜とあさりのうまみが、頬をゆるませる美味しさだ。
勉はクラムチャウダーの味が残っている間に、トーストを千切って口の中に放り込んだ。さっくりしたトーストの甘さが、チャウダーの味を引き立てる。
「うーん」
勉がうなって眉を寄せたので、日咲子はおそるおそるといった様子で、アイスティのグラスを置いた。
「……まずかった?」
「ごめんごめん、違うよ。ちゃんと美味しい」
「じゃあ、どうしたの?」
「俺も料理は苦手じゃないだろ?」
「うん?」
語尾に疑問符をつけながら二人は会話を続ける。
「このチャウダーだって作り方知ってるのに、俺が作ると同じ味にならないんだよね。何が悪いんだろうと思ってさ」
「愛情の差じゃない?」
真顔で答える日咲子に向かって、勉は少々意地の悪い目を向けた。
「わかった。夕食は野菜たっぷりの和風煮込みハンバーグにしようと思ってたけど取りやめな」
勉の言葉が終わるか終わらない間に、ぱっと日咲子が頭を下げる。
「言いすぎだった! 反省します!」
「いつも思うけど、変わり身早いよな……」
日咲子うんうんと頷いて、勉の追及を受け流した。
「冗談はおいておいて、たぶんこれが、特別なスープだからだと思う」
「特別って?」
「わたし、小さい頃から身体弱かったでしょう。おまけに今より食が細くて、その上好き嫌いも激しくて、お母さん達を心配させてたんだよね。栄養あるものを食べさせようって、お母さんがあれこれ知恵をしぼって考えてくれたレシピなんだ。わたし、牛乳は好きだったから、それに合わせたら野菜や貝なんかも食べられるんじゃないかって」
日咲子は、昔を懐かしむように、目を細めた。
「ほら、日咲子。ミルクさんとあさりさんが、カップの中でパーティしてるよ。野菜さん達もたくさんお呼ばれしてるよ、なんて言ってさ」
勉は、なんだかそこに幼い日咲子と若かりしころの義母がいるような気がした。
きっと、子供の日咲子はおそるおそるチャウダーを口にしたはずだ。そして――。
「わたし、あさりなんて大嫌いだったから、ほんとうにおっかなびっくり食べたんだよ。そしたら、すごく美味しかったの。あれえ、あさりってこんな味だったっけって思ったくらい。おかわりしたら、お母さんすごく喜んで。わたし、お母さんのあの顔、ずっと忘れないと思う」
だからね、と日咲子は言った。
「クラムチャウダーを作るときはいつも感謝の心で作るんだよ。ただ作るだけじゃだめなの」
「なるほど」
勉が頷くと、日咲子はクラムチャウダーをひと匙すくいあげた。ミルクのベールをまとったあさりが顔をだす。
「この味は勉君には作れないよ。お母さんの愛情と、わたしの感謝の心で出来上がってるんだもの。食べたくなったら、わたしがこんな風に作ってあげる」
ふと、日咲子の顔が輝いた。
「そうだ、勉君は勉君の感謝の気持ちで、クラムチャウダーを作ればいいんだよ。そうすればきっとまた違った美味しさのクラムチャウダーが出来るよ」
微妙に論点がずれてきたな、と勉は苦笑する。しかし、日咲子は上機嫌で手を叩いた。
「うん、それっていいと思うな。勉君、感謝だよ」
「俺は何に感謝して作ればいいわけ?」
「そんなの決まってるじゃない。こうやって二人で楽しく食卓を囲める事にだよ」
確かにそれは感謝かもしれないと勉は頷いた。