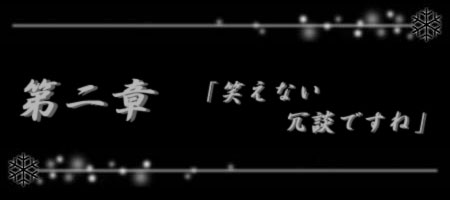
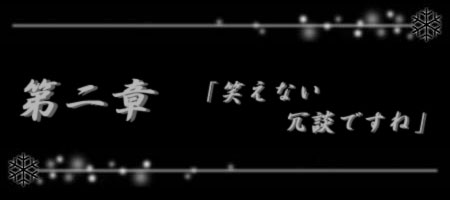 |
| 高い金を払っただけの事はあって、一番安いシチュウとレモネードは美味しかった。 特にレモネードは貴重なハチミツが使われていて、とても好みの味だった。 毎回注文してしまいそうで、怖い。 あんなのを毎回頼んだら、破産だ。 カレブは己を戒めた。
見上げると、灰色の空から雪が舞い降りてくる。
「これが、全部金貨なら苦労しなくていいだろうな」
差し出した手にふわりと落ちた雪は、呆気なく溶けて、消えた。
「ふふ、手にした途端、消える金貨なら、無い方がまし、か」
手にした途端、消える幸せなら、夢見ない方がましなのと、同じように。
「ま、きちんと働けって事だよね」
あり金をすられたというのに、戦士はまったく気づかなかった。
「あんな様子で、このご時世を生きていけるのかしら」
本人が聞いたら、余計なお世話だと怒鳴り出すような事を、カレブは思った。 ひきあげようか、それとももう少し働くか・・・
思案しながら道を見回していたカレブの目に、ふと一人の剣士の姿が飛び込んできた。
くるりときびすを返そうとしたその途端。
「・・・・・・少年」
よく通る声が、カレブの足を止めた。
カレブは辺りを見回し、「少年」が自分だという事を確認すると、顔を引きつらせる。
「ぼ、ぼく、ですか?」
白髪の剣士は、無言で頷く。
「何か、御用でしょうか・・・」
しぶしぶカレブはそう言った。
「手を、貸してもらいたい」
だが、剣士はそんなカレブにかまう事無く、静かにそう言放った。
「手を・・・?」
何か、もっと、とんでもない事を言われると思っていたカレブは、思わず剣士を見つめる。
そして、ああ、と思った。
ぼくは、この人の瞳が、苦手なんだ。
「私は、見てのとおりの傷ついた身体だ。歩くのが、少し辛い。酒場まで、手を貸してもらいたい」
カレブは迷った。
剣士の頼みは、特に難しくも何ともなかったが、カレブの本能は未だに「危険」を発していたからだ。
よろり、と剣士が一歩カレブに近づく。
カレブは、小さくため息をついた。
危なくなったら、自慢の俊足で逃げればいい、そう思ったからだ。
「わかりました。じゃあ、つかまって」
剣士に肩を貸して、カレブは歩き始める。
剣士が行きたいと言ったのは、カレブが食事をした「月夜亭」だった。
「それじゃ、ぼくは、これで」
立ち去ろうとしたカレブの腕を、剣士がつかんだ。
「待て」
ぎくりとして、カレブは身体を強張らせる。
「な、なんです!」
「・・・・・・若く、健康な身体だな。これなら、いくらでも働けるだろう。何故、盗みなどを働く?」
冴えざえとした青い瞳が、射抜くようにカレブを見ていた。
高鳴る心臓をなだめながら、カレブは笑みを浮かべる。
「おっしゃる事が、よくわかりません」
フ、と剣士も笑った。
「なかなかの胆力だ。私に見つめられて、笑えるとは」
笑みを顔にはりつけたまま、カレブは答えた。
「証拠もないのに、決め付けられるのは迷惑です」
「そうか」
追求されるかと思ったが、意外にも剣士はそう言って手を放した。
「寒さで、脳の血管がつまって、記憶障害を起こしているらしいな」
笑みが、消えていた。
思わずカレブは息をのむ。
これ以上は危険だ、と心の声がした。
「笑えない冗談ですね。では、ぼくはこれで」
くるりと背をむけると、一気に走り出す。
とたんに、ゾクリと背筋を走る悪寒。
「・・・え?」 真っ赤な何かが、足元の雪を染めた。
誰かの悲鳴が聞こえる。
「な、なん・・・だよ・・・」
カレブは、自分の胸から生える剣の切っ先を、呆然として見つめた。
「お前は二つ、罪を犯した」
剣士が、背後からカレブに語りかける。
「一つは、街中で盗みを働いた事」
目の前が、歪んでいく。
「一つは、この私に嘘をついた事」
ひどく、胸が痛かった。
「禁を犯した者は、裁かれなければいけない」
こんな所で、死んでしまうのだろうか。
嫌だ。
こんな、あっさりと死ぬわけにはいかない。
だって、ぼくの命は。
「身をもって、自らが犯した罪を知るがいい」
ドゥーハンを包む雪の如く、冷たい声が響いた。
だが、その声すらも、カレブにはもうあまり届いてはいなかった。
意識が途切れる寸前に脳裏をよぎったのは。
何故か、一面の青空だった。 |