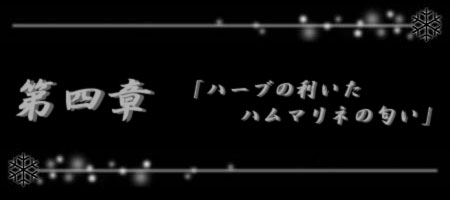
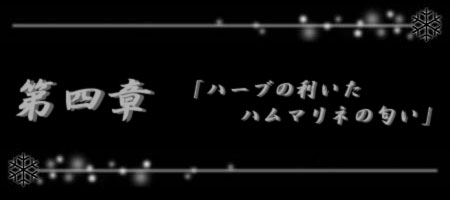 |
|
「よくこんなお金があったねえ」
「やかましい」 買ったばかりの短剣の具合を確かめるカレブを、リカルドは睨みつける。 「あの剣士の頼みじゃなかったら・・・、頼みじゃなかったら・・・」 迷宮探索に必要な装備を何一つもっていないカレブの為に、リカルドはとんだ散財をするはめになった。 「畜生。せっかくあの後稼いだって言うのによ・・・」 ぶつぶつと文句を言い続けるリカルドに、カレブは疑問をぶつけてみた。 「あのさあ? 聞きたかったんだけどね」 「なんだよ」 怒りながらもきちんと答えるあたり、リカルドの人のよさが滲んでいる。 「ここの人達ってすごく金貨を持っているよね。あんたもあの後、あっさりもうけたみたいだし・・・。どうして?」 「・・・・・・迷宮が、あるからな」 カレブは首を傾げる。 「王室が、迷宮探索を奨励してる。なんだってあんなもんがあそこに出来たのか調査しているらしいんだ。だが、手ごわい魔物がうじゃうじゃいて、兵士の数が減っちまったらしい。そこで、冒険者にも迷宮を調べさせる事にしたんだ。魔物を倒せば、王室から金が出る。市民は、金を得た冒険者を相手に商売して、もうける。こうやって奇妙な流通形態が出来上がっているのさ」 「ふうん」 カレブは目を細めた。 「迷宮なんてほっておいて、国をなんとかすればいいのに。聖都だけうるおったってしょうがないだろ。辺境の村や町はどうなるのさ」 「そんな事、俺が知るかよ。大体手前はコソ泥だろ? そんな心配するなんて笑えるね」 「・・・・それもそうだね」 ニッとカレブは笑った。 「痴話喧嘩は済んだか」 ぼそりとグレックが呟く。 「早く行かねば、日が暮れるぞ」 「ああ、そうだな。そろそろ行こう。まったく、難儀な奴に依頼を受けてもらったものだぜ」 「・・・地下一階の最深部まで行き、依頼が達成出来そうにないと思った時は、解除して良いとあの剣士は言った。ひとまず、そこまで行って見る事だな。この少年もあの剣士に見込まれたのだ。意外と頼りになる奴なのかも知れん」 グレッグの生真面目な言葉に、盛大にリカルドはため息をついた。 「グレッグさんよお・・・。あんた、それ、本気で言ってる? 迷宮、潜った事ナシ。戦闘経験ゼロ。魔法知識ゼロ。特技、スリ。そんな奴が、頼りになるか!!」 「本当にねえ」 しみじみと頷くカレブに、リカルドの眉が跳ね上がる。 「手前が言うな!!」 「まあ、なんにせよぼくもさっさと自由の身になりたいんでね。あんた達の依頼を終わらせて金をもらって、あの剣士と縁を切る。そんなわけだから、早く行こうよ」 「・・・・・・勝手な奴」 リカルドは小さく呟くと、兜をグイと目深に下ろした。 |
|
|
|
迷宮までの道すがら、リカルドはブツブツ言いながらも、カレブに迷宮での心得を教えてくれた。どうやら、本当にお人よしらしい。
「そんなわけで、けっこう手ごわい魔物もいるから。まずは手前は後ろで見てな。俺とグレッグで何とかするからよ」 「そうだな。その方が良いだろう」 無駄に怪我などしたくないカレブは、素直に頷いて見せた。 「ああ、でもさ、忍者さん」 「なんだ」 呼びかけられてグレッグが振り向く。 「あんた、恐怖を抱いてるんだろう? 魔物を前にして、しりごみしないでよね。ぼく、死にたくないから」 言った途端、リカルドの鉄拳が飛んできた。 「手前、デリカシーってもんがないのか!」 「ぼくに、そんなもの求めないでよ」 器用にこぶしを避けながら、カレブは呟く。 くっ、とグレッグが苦笑した。 「それくらい、正直なほうが気分が良い。私が負け犬だという事実は変わらんしな」 「あんたが良いなら、これ以上は言わないけど」 リカルドは天を仰いだ。 「遠い・・・。はるかに遠いぜ、信頼は」 一階の最深部でお別れだな、とカレブは思った。
「あれが?」 「ああ、そうだ。気を抜くんじゃねえぞ」 緊張した面持ちでリカルドが言う。 「あんたこそ、もうちょっと肩の力抜いたら?」 「黙れ、新人」 グレッグは無言で歩を進める。 だが、ふと足を止める。 「ねえ、なんだか匂わない?」 前を行く二人も足を止め、くんくんと鼻をうごかした。 「言われてみれば・・・」 「正解だどー」 しゃがれた間抜けな声が響いた。 オークは、ぽかんと口を開ける三人に向かって、親しげに話し掛けた。 「オダ、キャスタっていうんだど。剣士様に言われて、お、お前達を待ってたんだな」 あの剣士、魔物と知り合いなんだ・・・ 絶対に縁を切ろう。カレブは固く心に誓った。 「剣士様って、あの白髪の剣士か?」 「様をつけるだど!」 キッとオークがリカルドを睨む。 「ああ、すまん、すまん」 素直に謝るリカルドに、カレブはとうとう吹き出した。 「オ、オークに謝るなよ!」 「うるさい、悪いと思ったから謝っただけだ。人とか、魔物とか、関係あるか!」 どうやらこの展開に慣れてきたのか、グレッグはカレブとリカルドを無視して、オークに話を聞く。 「我々を待っていた、とは。何用だろうか」 「こで。あんた達にわだせって。僧侶がいないから、怪我したら、だいへんだからって」 オークのキャスタは、いくつかの薬瓶をグレッグに手渡した。 「これは、傷薬。かたじけない」 「カレブってのは、あんただか?」 「いや・・・」 グレッグは首を振ると、カレブを指差した。 「彼がカレブだ」 キャスタは、とことことカレブに近寄る。 「剣士様からの伝言だど」 カレブは嫌な顔をした。 「まじめにやらないど、また、寺院送りにするっで。逃げても、おっかけるっで。剣士様の命令は絶対だ。ちゃあんとやるだど?」 じっと自分を見つめるつぶらな小さな瞳に、カレブはげんなりした。 「わかった。だから、そんな目でぼくを見るな」 カレブのわかった、という言葉に満足したのか、キャスタはにいっと嬉しそうに笑った。 リカルドが、鼻をこする。 「この妙な匂い、お前のだな。でも、どうも普通のオークの匂いとは違うような。連中はもっとこう、気分が悪くなる匂いがするんだが」 確かに妙な匂いだが、胸が悪くなる、というものでもない。 「オダ、きれい好きなんだど。だから、ちゃあんと水あびするだ。ハーブでからだ、こすってるだ。だから、いい匂いなんだな」 ハーブ、という言葉にリカルドが反応した。 「ああ、それでかあ! どうりで、どっかで嗅いだ事があると思った。アレだ、アレ。あの匂いだ」 「アレじゃわかんないよ。何の匂い?」 「ハーブの利いたハムマリネの匂いだ!」 カレブはリカルドに回し蹴りを食らわせた。 「二度と食べられなくなるだろ、この馬鹿戦士!!」 キャスタが、カレブの第二撃を止める。 「な、なかまわれはダメだど! ああ、やっぱり剣士様のいうとおりだ。オダがちゃんとついて行って、見張ってないとダメみたいだどー」 「・・・・・・なんだって?」 カレブは、キャスタをにらみつけた。 「オダ、お前達についていくだ。オダ、剣士様にお前を見張るように言われただ」 リカルドが、カレブの肩に手を置く。 「オークが見張りだなんて、信用ないんだな、やっぱり」 「・・・・・・コソ泥だからね」 苦りきった声で、カレブは答えた。 |